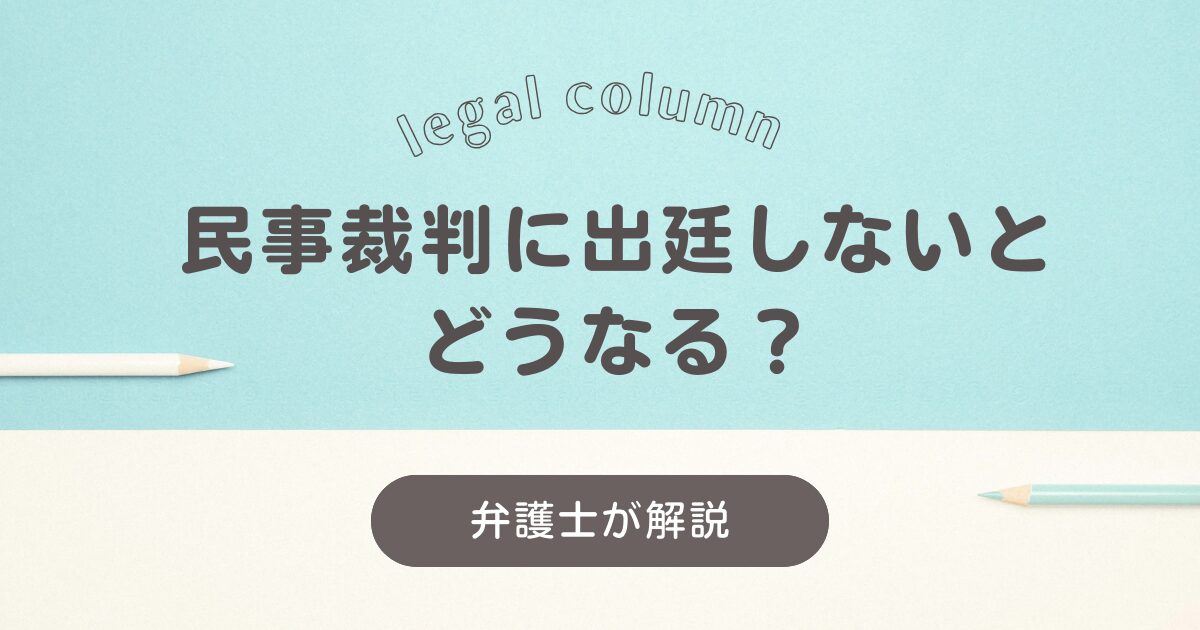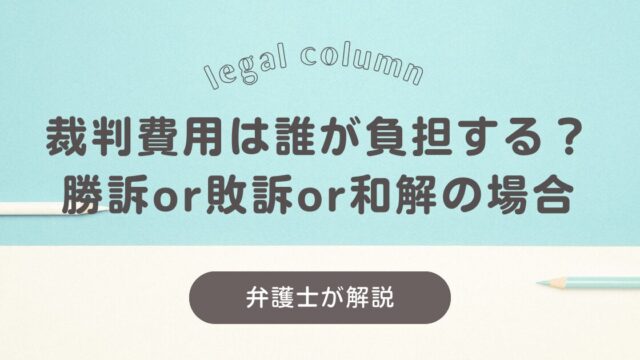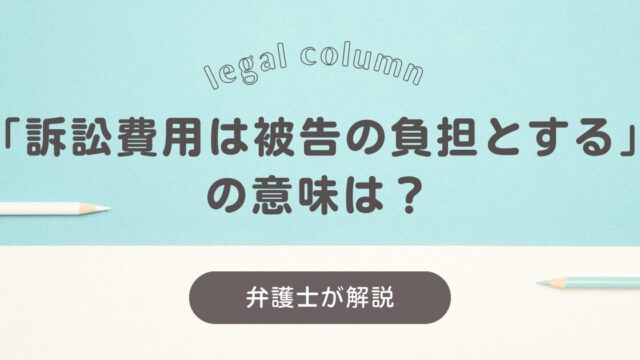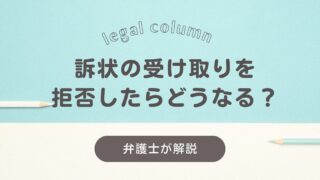民事裁判に出廷しないとどうなるのでしょうか。また、裁判で訴えた相手が来ない場合、その後の裁判はどうなるのでしょうか。
1回くらい裁判に欠席しても問題ないだろうと甘く考えている方もいるかもしれません。ところが、裁判所からの連絡を無視して裁判を欠席した場合、いわゆる欠席判決になってしまい、取り返しのつかない不利益を受けるおそれがあります。
今回の記事では、民事裁判に原告が出廷しない場合、被告が出廷しない場合、2回目の欠席をした場合、答弁書提出と欠席の関係などについてご説明します。
- 原告が民事裁判に出廷しないとどうなる?
- 被告が民事裁判に出廷しないとどうなる?
原告が民事裁判に出廷しないとどうなる?
- 原告が初めて欠席をした場合
- 原告が連続して2回目の欠席をした場合
- 本人尋問に欠席した場合
原告が初めて欠席をした場合
原告が民事裁判に初めて欠席したとしても、その後も裁判が続けられることがほとんどです。
体調不良等のため欠席の事前連絡をした場合
原告が、裁判期日前に、裁判所へ欠席する旨連絡をしたとします。
体調不良や事故など欠席の理由がやむを得ない場合、裁判所は被告へ連絡をとって、期日を変更してもよいか協議することが多いです。被告だけ裁判に出席しても、期日を開く意味がないことが多いからです。期日が変更されれば、そのまま裁判は継続されます。
被告が期日の変更を拒否するか、そもそも欠席の連絡が期日直前で調整する時間の猶予がない場合などは、そのまま予定どおり期日が開かれます。
こうして期日に被告だけが出席した場合、裁判所は、被告の都合を聞いた上で、次回の期日の日程を決めることになります。このように、問題なく裁判が継続することがほとんどです。
無断欠席の場合
原告が裁判に無断欠席した場合、被告としては自分は裁判所に出頭したとしても欠席扱いにしてもらうことがあります。なぜかというと、原告と被告の双方が欠席した場合、1ヶ月以内に期日指定の申立をしないと、訴えの取り下げがあったものとみなされるからです。
これを「休止満了(きゅうしまんりょう)」といいます。
【引用】民事訴訟法263条前段
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
訴えられている側の被告としては、訴えの取り下げで裁判が終了すれば、もうその後の対応が不要になるので、休止満了を希望する人が多いのです。
もっとも、この場合でも、原告は1ヶ月以内に裁判所へ連絡をして、期日指定の申立をすれば、問題なく裁判を継続することができます。
また、裁判の初回期日に無断欠席したわけではなく、これまでの期日には問題なく出席していた原告が、たまたまある期日にだけ欠席した場合には、そもそも被告を欠席扱いすることなく、普通に次回期日を入れて裁判を継続させることも多いです。
このように、原告が民事裁判に無断欠席したとしても、1回目の欠席であれば、問題なく裁判が継続できることがほとんどといえます。
原告が連続して2回目の欠席をした場合
原告が2回連続で裁判に欠席すると、裁判が終了してしまう可能性があります。
以下の条文を見て下さい。
【引用】民事訴訟法263条後段
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
これは、「当事者双方」が2回連続欠席した場合の規程ですが、先ほど説明したように、被告は裁判所に出頭しても、原告が来てない場合には自分も欠席扱いにしてもらうことができます。そのため、原告が2回連続欠席した場合には、双方が2回欠席した扱いにされることがあります。
この場合、直ぐに裁判は取り下げたものとみなされてしまいます。1回目の欠席と異なり、1ヶ月間の猶予もありません。
ただし、原告が事前に裁判所へ欠席の理由を連絡している場合には、その理由次第では、2回連続欠席しても裁判を継続してもらえることもあります。
本人尋問に欠席した場合
原告が本人尋問に欠席した場合、原告の尋問を行なうことはできません。尋問をしなければボロがでないので有利なのではと考える人もいるかも知れませんがそうではありません。尋問をしなければ、陳述書として書面で提出した証拠の意味がほとんどなくなってしまいます。
その結果、原告と被告で争いのある事項について、被告が陳述書に書いたことや尋問で話したことが認められてしまうことが多いです。
原告が弁護士に依頼している場合
原告が弁護士に代理人になることを依頼している場合には、原告本人は裁判期日には出席しないのが普通です。原告本人が出席していないからと言って、裁判のやる気がないわけではありません。ただし、本人尋問を行なう期日だけは原告本人も出席する必要があります。
被告が民事裁判に出廷しないとどうなる?
- 答弁書を提出して初回の期日に欠席するのは問題ない
- 答弁書を提出しないで欠席した場合
答弁書を提出して初回の期日に欠席するのは問題ない
被告が、最初の裁判期日に欠席すること自体は珍しくありません。最初の期日の日時は、被告の都合を聞かずに勝手に決められることがほとんどだからです。
もっとも、被告が最初の裁判期日に欠席するのであれば、必ず期日までに答弁書を裁判所へ提出しておく必要があります。
民事裁判の最初の期日では、答弁書を事前に提出しておけば、裁判に欠席しても、答弁書の内容を主張したとみなすことになっています。
そのため、答弁書が期日までに提出されている限り、裁判所は原告と被告の都合を確認して2回目の期日を決め、審理を続行することがほとんどです。
なお、弁護士に依頼していない場合、2回目からの期日は基本的に出頭しなければならないので、注意しましょう。
答弁書を提出しないで欠席した場合
最初の期日に欠席すると欠席判決で敗訴する可能性がある
被告が、裁判所に答弁書を提出せず、最初の期日に出廷しなかった場合、どうなるのでしょうか?
このような場合、裁判所は、被告が原告の主張する事実を全て認めたとみなすことになっています。
例えば、300万円の貸金返還請求の場合、原告が被告に300万円を貸したこと、被告が1円も返していないことが全て争いのない事実だと判断され、原告の請求が全て認められることになります。
そうすると、裁判所は、これ以上審理を続ける必要がないので、初回の期日で弁論を終結し、判決言渡しの日を指定して第1審の審理手続を終了することになります。弁論を終結すると、第1審の審理手続が終了するので、それ以降は新たに主張や証拠を提出することができません。
このように、被告が裁判所に何の連絡もせず、答弁書も出さず、初回の期日に出廷しなかった場合には、原告の請求を全て認める判決が言い渡され、敗訴するリスクがあります。これを欠席判決と呼びます。
欠席するのに答弁書の提出が間に合わなそうなとき
第1回目の期日に出頭できないのに、答弁書を提出する時間もないという場合には、必ず事前に裁判所に連絡して、期日に行けない理由と答弁書をいつまでに提出する予定かを説明する必要があります。
この場合、裁判所は、あなたの説明を聞いた上で、弁論を終結せず審理を続けるか、最初の期日で終結するかを判断します。体調不良等が理由で答弁書の作成が間に合わないし期日にも行けないのであれば、しっかりとそのことを説明しましょう。ただし、続行するかどうかは裁判官の判断なので、絶対に終結しないとは言い切れません。
欠席のまま弁論が終結してしまったときには、直ぐに裁判所に連絡を取ってみる
もし、最初の期日までに裁判所への連絡が間に合わず、次回が判決言渡し日となってしまった場合、どうすればいいでしょうか。
この場合でも、主張したいことがあったり、審理をして欲しいことがあれば、裁判所に連絡をして希望を伝えること自体は可能です。
裁判官によっては、被告の説明を聞いた上で、弁論を再開し、審理をするということもあり得ます。ただし、これも裁判官の判断なので、必ず弁論が再開されるとは言い切れません。
なお、判決の言渡しが終わった後では、もはや弁論を再開することはできません。判決に不服がある場合に、控訴することになります。
被告が弁護士に依頼した場合
被告が弁護士に代理人になることを依頼したのであれば、裁判期日には、被告本人は出席しないのが普通です。被告本人が裁判に出席しなくとも、不利になったり、咎められたりする理由はありません。ただし、原告と同様に、本人尋問を行なう期日には、被告本人も出席する必要があります。