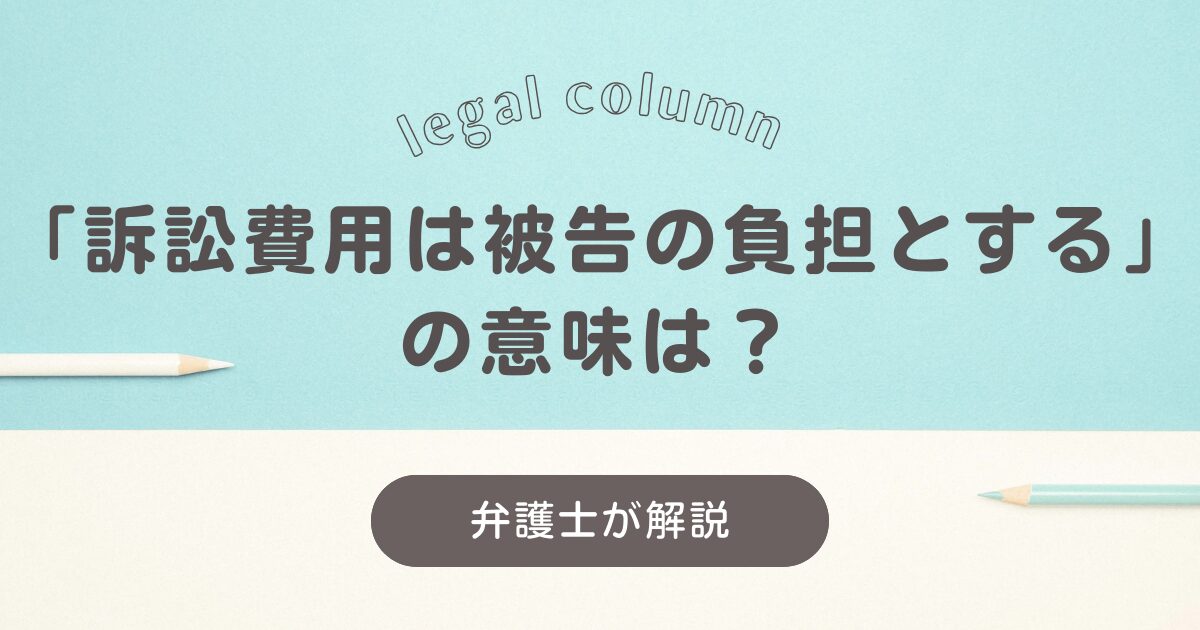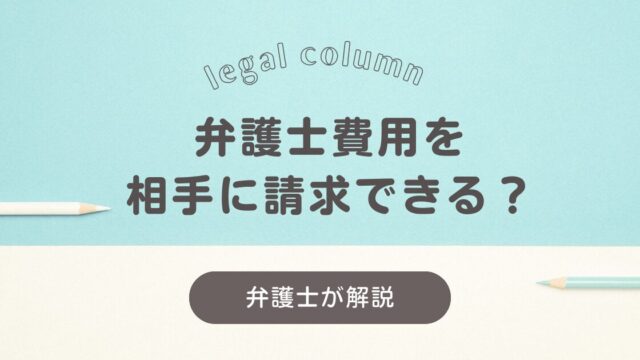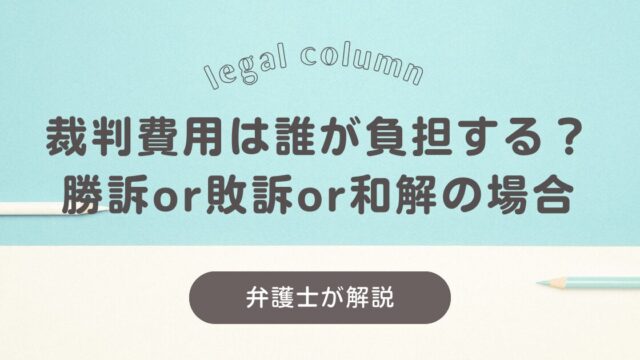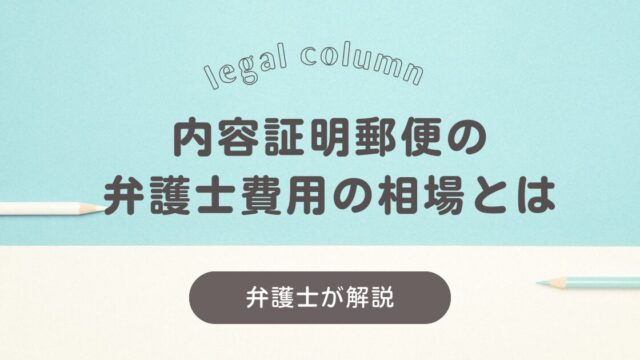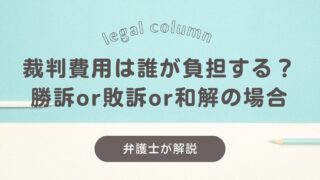- 「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が届いたら・・
- 「訴訟費用は原告の負担とする」ときもある?
- 訴訟費用の負担割合はどうやって決まる?
- 和解の場合は「訴訟費用は各自の負担とする」
- 実際には訴訟費用の請求はしないし、されないことがほとんど
「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が届いたら・・・
あなたが訴えた側(原告)の場合
「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が確定しても、訴えた相手に弁護士費用を請求できるワケではありません。この判決に書かれている「訴訟費用」には弁護士費用は1円も含まれていないからです。
「訴訟費用」にどのようなものが含まれているのかは、▶民事の訴訟費用一覧|計算方法や相場も解説の記事を参考にしてください。
では、提訴時に裁判所へ納めた収入印紙などの「訴訟費用」は、「訴訟費用は被告の負担とする」という判決があれば請求できるのかというと、そうではありません。まだ、具体的な金額が記載されていないから、相手は訴訟費用をいくら払えば良いか決まっていないからです。
実際に訴訟費用を相手に請求するためには、訴訟費用額確定処分の申立を行なう必要があります。これは、▶訴訟費用額確定処分の申立方法と流れ(訴訟費用の請求方法)の記事を参考にしてください。
理由は後ほど説明しますが、実際には訴訟費用額確定処分の申立はせずに、メインの請求部分についてのみ、相手に対して支払うように連絡するのが通常です。ただし、相手が了承しさえすれば、訴訟費用確定処分を行なうことなく、印紙代くらいであれば払ってもらうことができることもあります。
あなたが訴えられた側(被告)の場合
「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が届いて、あなたは控訴しなかったとします。
その時点では、メインの請求については支払う義務が生じていますが、「訴訟費用」については具体的な金額が決まっていないため、直ぐに支払う義務があるわけではありません。
実際には、判決が確定した後も、訴訟費用以外のメインの請求部分の金額請求しかされず、その部分を支払えば、訴訟費用は請求されないことも多いです。
「訴訟費用は原告の負担とする」ときもある?
訴訟費用は必ずしも被告負担になるわけではありません。訴訟費用はというのは、「訴えられた人」が負担するものではなく、あくまで「敗訴者」が負担するものだからです。
民事訴訟法第61条(訴訟費用の負担の原則)
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
そして、裁判中に和解できずに判決に至った場合には、判決の中で訴訟費用の負担者が定められます。
敗訴者負担なので、裁判で原告が全部勝った場合(請求が全部認められた場合です)には、判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」とされますが。
逆に、被告が全部勝った場合(請求が全部認められなかった場合です)には、判決で、「訴訟費用は原告の負担とする」とされるのです。
訴訟費用の負担割合はどうやって決まる?
裁判はどちらかが100%勝つものだけではなく、一部勝訴、一部敗訴の判決になることも多いです。
この場合、法律によると、訴訟費用の負担割合は裁判所が裁量で定めるとされています。
民事訴訟法第64条(一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
実際の訴訟費用の負担割合は、請求額のうち判決で認められた金額の割合と同じくらいの割合になることが多いです。
例えば、1,000万円請求して、700万円だけ認められた場合、訴訟費用の負担割合は、原告(請求側)が10分の3を負担し、被告側(請求された側)が10分の7を負担するように定められることが多いです。
このときは、「訴訟費用はこれを10分し、その3を原告負担とし、その余を被告負担とする」のような判決になります。
和解の場合は「訴訟費用は各自の負担とする」
訴訟中に和解する場合には、和解条項の一つとして、「訴訟費用は各自の負担とする」という条項を入れることがほとんどです。
この場合、和解までに双方が訴訟費用として裁判所に払った実費等があったとしても、払った人が負担することになります。
仮に、高額な印紙代や鑑定費用を一方当事者が支払っており、その分を考慮して和解内容を決めるときであっても、訴訟費用の負担割合を定めることはまずありません。考慮した分は和解金額自体にまとめてしまうことがほとんどです。
なぜかというと、訴訟費用の負担割合をだけを定めても、その後に訴訟費用額確定処分という面倒な手続する必要があるからです。
実際には訴訟費用の請求はしないし、されないことがほとんど
これまで見てきたように、判決になった場合には、訴訟費用の負担者が決められます。
ところが、実際には、訴訟費用を相手に請求することも、そのために訴訟費用額確定処分を申し立てることもほとんど行なわれていません。
多額の鑑定費用などがかかっており、原告側がほとんど予納金を裁判所に払っている場合など、限られたケースでしか訴訟費用の請求はされていないのが現状です。
私の経験上は、判決が出ても訴訟費用額確定処分をするケースというのは100件に1件もないのではないかと思います。
これはなぜかというと、訴訟費用確定処分を行なうのに手間がかかるからです。
単に手間がかかるだけなら良いのですが、簡単にできるものでもないため、弁護士に依頼すると、訴訟費用以外に弁護士費用がかかってしまうため、訴訟費用が高額でない限りは、費用対効果を考えて、わざわざ行なわないという理由もあります。
まとめ
訴状の請求の趣旨や、判決書の主文の「訴訟費用は被告の負担とする」という記載の意味について、これまでの説明をまとめると次のとおりです。
民事裁判で訴えられた側(被告)が裁判で負けると、メインの請求についての判決以外に、「訴訟費用は被告の負担とする」という判決がされます。
ただし、この判決の「訴訟費用」には弁護士費用は含まれていないので、相手の弁護士費用を払う必要はありません。
また、「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が確定した時点では、また訴訟費用の具体的な金額が決まっていないので、訴訟費用を払わなくても法的には問題ないです。
具体的に支払義務を負うのは、訴訟費用額確定処分がされてからですが、実際には申立をしないorされないことが多いです。
このため、判決確定後に訴訟費用が請求されないことも多いです。
ただし、相手が訴訟費用の支払を求めている場合には、それが明確な費用(訴え提起時の印紙代や鑑定のための予納金)であるときは、任意に支払った方がお互い手間がなくて良いこともあります。